「痛みを避けて動いていると姿勢が前かがみになる」
「前かがみの姿勢で歩くのが恥ずかしい」
「脊柱管狭窄症と診断されてリハビリをしているが以前のように歩けるんだろうか?」
脊柱管狭窄症は姿勢から戻していかないと悪化する恐れがあります。
こちらでは脊柱管狭窄症になる原因と解決法について書いています。

胸郭の影響とは
胸郭とは肋骨と背骨に囲まれている部分を指し、この胸郭が上下に動くことで心肺機能を助けるのです。
加齢とともに運動不足の人は、呼吸が浅いので胸郭の動きが少なくなっています。
そして胸郭は単独で動くのではなく、腰部と頸椎に加えて肩甲骨の動きにも左右されます。
この胸郭の柔軟性の低下は、反り腰を引き起こす原因の一つとなるのです。
その理由は肋骨まわりの硬さにより呼吸が浅くなり、無意識に姿勢が悪化する可能性があるからです。
肋骨まわりが硬いと空気を取り込む際に肋骨がスムーズに開かないので、無意識に腰を反ることで胸郭を引き上げようとします。
結果として反り腰を誘発し、反り腰になることで姿勢が歪んでいくのです。

反り腰が悪化すると
反り腰とは腰椎の前弯が強くなっている状態で、腰が反らされることで脊柱管が狭くなり神経や血管を圧迫します。
神経や血管が圧迫されることで脊柱管狭窄症になりやすくなり、太った人は特に反り腰が悪化しやすく坐骨神経痛が起こりやすくなります。
高齢者では、太ももの前にある大腿直筋が過緊張して股関節が曲がった反り腰も多くみられます。
この股関節の曲がりは、さらに変形性膝関節症を誘発するので注意が必要です。
大切なのは胸郭の柔軟性を高めて、反り腰を誘発させずに動きやすい姿勢を作ることです。
胸郭を柔らかくするスマート筋トレ
胸郭の柔軟性を高めるためには肩甲骨と背骨を動かすのが大切です。
やり方)
- 背筋を伸ばして両腕の肘を曲げる
- 両腕の肘を胸の前でつけて開く
次は背骨を捻じります。
- 足を肩幅に開いて立つ
- 両足を交差して上半身を捻る
最後は肩甲骨と背骨を同時に動かします。
- 足を肩幅に開いて立つ
- 右手を上に反らして左足も後ろに反らす
- 逆側も同様に行う
動画も参考にしながら行ってください。
基本的に思いっきりする必要はないので、軽めでやっても十分な効果が得られます。

まとめ
脊柱管狭窄症は背骨の柔軟性が低下し、反り腰になるせいで起こります。
ですが背骨だけを動かしても脊柱管狭窄症は根本的に解決されません。
胸郭の動きを制限している肩甲骨の動きを高め、普段から胸郭の体操を続けることで脊柱管狭窄症は解消されます。
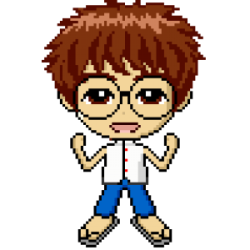
新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願致します🙇♂️⤵️
先月あたりから、昔の古傷が出始めて辛いですが頑張って参ります❗️