アレルギーは身体からのサインだと知っていますか?
「免疫力の低下」
「炎症が起こるから」
「アレルゲンが増えるから」
これらの情報はどれも正解ですが、実はアレルギーは体質の影響が最も大きいと言えます。
今回のブログを見ればアレルギーが起こる体質の仕組みと、花粉症などを解消するのに必要なことが分かります。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします
アレルギーは体質のサイン
東洋医学ではアレルギーをアレルゲンに対する過剰な反応ではなく、身体に何らかの問題が起こっていると考えます。
東洋医学で重視しているのが身体の巡りであり、気血水がきちんと巡っていればアレルギーなどの反応は起こりません。
ですが、五臓六腑の機能が低下し、気血水の巡りが悪くなり身体のバランスが乱れる事でアレルギーが起こると考えています。

気血水の中でもアレルギーの原因となりやすいのが水の巡りであり、水は血管の外側にある色々な水分の総称です。
水にはリンパや関節液、胃腸の消化液など様々なものが含まれますが、どこかの巡りが悪いと身体全体に悪影響を及ぼします。
そのため、アレルギーを解消するには原因となっている水の巡りの悪さを解消する事が重要となります。
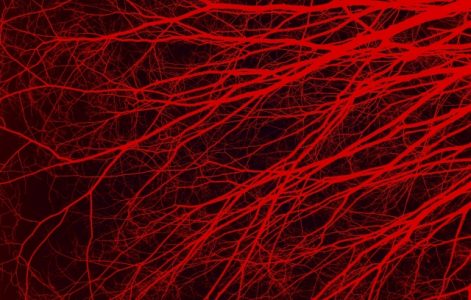
アレルギーは「肺」と「免疫」の不調から
東洋医学ではアレルギーと最も関係が深いのは肺としており、肺は全身へ水を運ぶ役割をしています。
そして肺は水を巡らせることで皮膚や粘膜を正常に保ち、結果として免疫力を左右していると考えています。
そのため、肺が弱る事でアレルギーが起こり、咳や痰が増えて炎症が鎮まりにくくなるとアレルギーは悪化します。

他にも脾から吸収された栄養が水を作り、不要な老廃物を含んだ水は腎から排泄される事で水の巡りを助けています。
肺が弱い人は脾も弱い傾向にあり免疫力が低く風邪を引きやすいのが特徴で、普段から疲れやすく息切れしやすくなります。
また、加齢に伴い腎が弱ると免疫力は一段と下がり、むくみが酷くなって足腰のダルさを訴えやすくなります。

花粉症とは
東洋医学では花粉症の原因は水の巡りが悪い水滞と捉え、冷え性だったり虚弱体質だったりする事も問題と考えます。
特に胃腸が弱い人は虚弱な体質になりやすいので、脾と肺の両方が弱いせいで花粉症になりやすくなります。
そのため東洋医学では花粉症の解消は身体を温める事を基本とし、胃腸を弱らせないために冷たい飲食は避けるようにします。

身体を温めるために運動を推奨し、6時間以上の睡眠をとることで疲れを溜めないようにする事も重視します。
基本的にアレルギーなどによる炎症が鎮まらない人は過労の傾向があり、睡眠不足の人も目立つので睡眠は重要です。
生活習慣を改める事で脾・肺・腎の機能が高まると花粉症の症状はマシになる事が多くあります。

まとめ
花粉症は水の巡りが悪い水滞が原因となります。
水滞は脾・肺・腎の機能が低下する事で起こりやすくなります。
大切なのは身体を温めて胃腸の負担を減らして睡眠時間を確保する事です。
⇒アレルギー体質を変える!大阪市北区で東洋医学の整体が受けられます