40代になってから不調が増えていませんか?
「頭痛が増えた」
「お腹が痛くなりやすい」
「足腰がだるい」
こんな症状は東洋医学から見たら体内に毒が溜まっているかもしれません。
今回のブログを見れば40代から毒が溜まる原因と、毒出しに必要なことが分かります。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。
ホルモンと代謝の低下が始まる時期
女性なら37歳が厄年で男性なら42歳が大厄となり、その頃から急激にホルモンと代謝の低下が始まります。
男女ともに性ホルモンの分泌が減少するとともに代謝が低下し、生活習慣病のリスクが高まるのが40代です。
特に女性はエストロゲンが減少する事で更年期障害のリスクが高まり、ホルモンのバランスが乱れる事で心身ともに不安定となります。

男性は筋肉量の減少が始まって代謝が低下する事で内臓の機能も低下し、糖尿病や高脂血症、高血圧などのリスクが高まります。
男女ともにこういった身体の変化に伴い体内には老廃物が溜まりやすくなり、溜まった老廃物が毒となり不調の原因となるのです。
そのため、40代はそれ以前と同じ生活をしていると不調に襲われやすく、場合によっては大病を患う事もあるのです。

気滞・血滞・水滞のタイプ別の特徴と対策
東洋医学で40代から特に問題視しているのは、身体の巡りが悪くなる事です。
身体を常に巡って健康を保っているのが気血水なので、気血水の巡りが悪くなることで様々な不調が現れます。
特に40代から巡らせる力が低下する事で気滞や血滞、水滞などの状態となり、特徴的な症状が現れます。
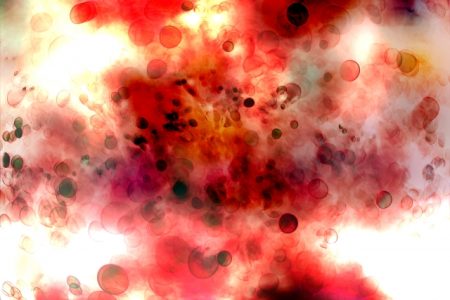
気滞とは熱が頭にこもった状態で、頭痛やめまい、肩こりなどの上半身の不調が多く現れます。
血滞とは血流が悪い状態で、身体の肌にクスミが出たり筋肉や内臓に痛みが現れやすくなります。
水滞は老廃物が溜まった状態で、腰痛や足腰のダルさ、倦怠感など下半身の不調が多く現れるのが特徴となります。

東洋医学式「毒出し力」の高め方
東洋医学で毒と呼んでいるのは巡りを邪魔している詰まりであり、そのため詰まりを取り除けば気血水の巡りが高まり毒は排泄されると考えています。
尿や便、汗を出すのも大切ですが、まずは気の巡りを高めるために運動する事が大切と考えています。
40代から問題が顕著になるきっかけは運動不足で、運動不足により筋肉量が減少するのが一番の問題となります。

そのため、40代からは意識して歩く距離を増やしたり階段を使う事が大切で、それに加えて水分をしっかりと補給する事が大切です。
汗をかく事で気滞と水滞は解消されやすくなり、水分補給をする事で血滞は解消されやすくなります。
そして筋肉を刺激する事で気血水の巡りは高まるので、まずは運動不足の解消を目指す事が毒出しには必要となります。

まとめ
40代からはホルモンと代謝が低下します。
東洋医学では気血水の巡りが悪くなるのを問題視します。
大切なのは運動をして水分補給を心がける事です。