東洋医学の事はどれくらい知っていますか?
「気血水とは?」
「現代医学との違いって?」
「そもそもどんな理論なの?」
こんな疑問を抱えている人は多いと思います。
今回のブログは東洋医学をまだあまり知らない人向けで、気血水の理論と気虚と血虚について解説しています。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。
気・血・水とは何か
気血水とは自然の関係性を人間の体内で現した言葉で、植物が栄養を吸収して太陽から熱エネルギーを受け取り成長する姿を表現しています。
そのため血は栄養など血管内の物質を指し、筋肉を動かすための栄養であり血が不足すれば全身の機能が低下します。
気は太陽から受け取る熱エネルギーのような存在で、内臓や骨格筋が本来の機能を発揮するのに必要です。

水は血管の外側を流れる液体の総称で津液とも呼ばれ、血から生まれ全身を潤したり活動を助け老廃物を排泄するものです。
気血水はどれも重要ですが東洋医学が重視するのは関係性で、血が不足した血虚の状態なら気は高まりませんし水も不足します。
また、気が不足し体温が低い気虚の状態では、血の吸収や生産が不足して血虚を招くという関係です。

気虚体質とは
気虚体質の人は体温が低い傾向にあり、現代の目安としては36.3℃以下が気虚体質と言えます。
体温が低い人は内臓の働きも低いために、食事をしても消化吸収が上手くできず多くは食べられません。
そのため、気虚体質の人は血虚の状態にもなりやすいのが特徴で、気虚と血虚は同時に起こりやすいのが特徴です。

気を高めるのに必要なのは運動をする習慣ですが、気虚体質の人は身体が弱いので運動を嫌う傾向にあります。
運動をしないから体温が上がらずに余計に気虚となり、代謝が低下する事で冷え性や意欲の低下を招きます。
また、総じて胃腸の機能が低いために下痢や腹痛を起こしやすく、人によっては強い倦怠感に襲われやすくなります。

血虚体質とは
血虚体質の人は血の消耗が激しい傾向にあり、人間の身体は脳や筋肉を使い過ぎる事で血の消耗が激しくなります。
また女性は生理の影響で生理後には血虚の状態になりやすく、血虚体質の人は女性の方が圧倒的に多くなります。
血虚は貧血とは違い不足しているのは赤血球だけでなく、栄養素やホルモンなども含んでいるので更年期の女性も血虚になりやすくなります。
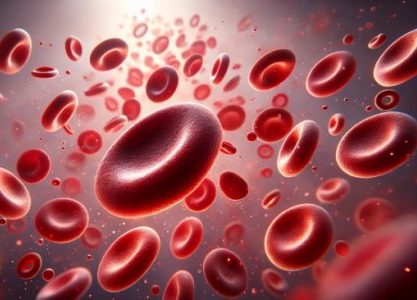
血の補充は食事で補うだけでなく睡眠も必要となるので、睡眠不足の傾向にある現代人には増えていると言えます。
そのため過労で睡眠不足が続くと男性でも血虚になりますし、日々の食生活で栄養の偏りがあっても血虚は起こります。
基本的に食事と運動、睡眠のバランスを保つ事で気虚や血虚は防げるようになります。

まとめ
東洋医学は身体の状態も自然の流れと同じと考えます。
気虚とは体温の低さや栄養不足から身体の機能が低い状態です。
血虚とは過労や睡眠不足による血の消耗が主な原因になります。
⇒自分の体質を知る!大阪市北区で東洋医学の体質診断が受けられます