最近、朝から疲れている、髪が抜けやすくなった、足腰がだるい…。
こんな症状に悩んでいるなら、それは東洋医学の腎のエネルギー不足かもしれません。
東洋医学では腎は生命力の源とされ、若々しさや意欲、ホルモンに代謝などに関わる体のエネルギータンクです。
今回はそんな腎の機能と現代医学との違いを解説し、朝から腎を整えるための習慣を紹介します。

東洋医学での腎は生命エネルギーの貯蔵庫
東洋医学では腎は単なる臓器ではなく、先天の精を蓄える場所とされ成長や生殖、老化、生命力に関わるとされます。
そのため、腎が弱ると白髪や抜け毛が増えて足腰のだるさが現れたり、冷えや耳鳴りなどの老化現象が出ると言われます。
つまり東洋医学の腎は生命エネルギーの貯蔵庫で、腎がしっかりしていれば若さも元気も長持ちするのです。

腎が弱った状態を東洋医学では腎虚と呼び、腎虚の症状には加齢性の難聴や耳鳴りが含まれます。
さらに骨や筋肉の衰えなども挙げており、これらの症状は現代医学から見ても腎機能の低下により現れる症状です。
また、腎虚の症状である疲れやすさや記憶力の低下なども、腎不全などの病気が引き起こす症状と同じです。

現代医学でいう腎臓と副腎とのつながり
東洋医学の腎の機能を現代医学で説明すると腎臓と副腎の機能に相当し、副腎から分泌されるホルモンの作用も含んでいます。
腎臓は老廃物の排泄と必要なものの再吸収を担当し、さらにホルモンを分泌して血圧や赤血球の数を調節しています。
そして副腎から分泌されるホルモンはストレス対応や炎症の抑制、さらに血糖値や塩分、水分バランスの調整などを行います。

他にもアドレナリンやノルアドレナリンなどを分泌して血圧や脈拍、血糖値を上昇させて心身を活発にさせる働きをします
あまり知られていませんが副腎からはアンドロゲンと呼ばれる性ホルモンも分泌されており、生殖器とは別に性ホルモンを分泌して体に影響を与えています。
女性ホルモンのエストロゲンは髪に影響し、減少すると抜け毛や白髪が増える一因となり副腎疲労の人も同じような症状が現れます。

朝:腎を目覚めさせる呼吸と温活
東洋医学では腎を元気にするには朝が大事とされ、朝に体温を上げておくことで腎の機能が高まります。
人間の体温は一般的に午前4時〜6時ごろが最も低く、体温が低い時は腎機能も低下しています。
そんな朝の時間に体温を上げることで腎機能が高まりやすくなり、血流を高める事で日中のパフォーマンス向上と疲労軽減に役立ちます。
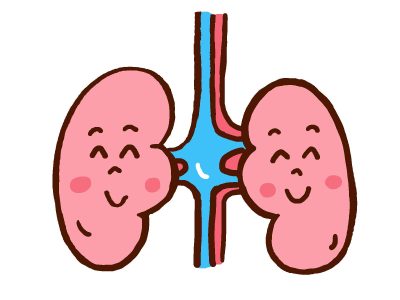
おすすめの習慣は朝にホットの黒豆茶を飲む事と、関元(かんげん)と腎兪(じんゆ)というツボを擦った後に行う逆腹式呼吸です。
関元と腎兪は体温を上げるのに役立ち、息を吸いながらお腹を凹ませ息を吐きながらお腹を緩ませる逆腹式呼吸で刺激する事ができます。
まずはへそ下にある関元と、へその裏側で背骨の両横にある腎兪を10回ほど擦り、5秒吸ってお腹を凹ませ10秒吐きながらお腹の力を緩めましょう。
逆腹式呼吸を5回ほど行うだけで体はポカポカと温まってきます。

まとめ
東洋医学の腎は成長や生殖、老化に生命力を司ります。
現代医学から見れば腎臓と副腎の機能を合わせた感じです。
腎を元気にするには朝にホットの黒豆茶を飲み逆腹式呼吸を行う事です。
⇒副腎疲労からの解放!大阪市北区で東洋医学の整体が受けられます