「寝ても疲れがとれない」「体がだるい」「風邪をひきやすい」
そんな悩みを抱えている人は東洋医学の気が不足している気虚(ききょ)タイプかもしれません。
今回は気虚とは何か、脾と肺との関係、そして気を補うストレッチと薬膳までをお伝えします。
今回も東洋インサイド整体院院長の福原がお送りします。
気虚とは
東洋医学でいう気とは体を動かすエネルギーで、呼吸と食事から得るエネルギーが合わさって作られると考えます。
この気が不足した気虚の状態になると、疲れやすく風邪をひきやすかったり、声が出にくく息切れしやすかったりします。
車でイメージするならアクセルを踏んでもスピードが出ないような状態で、本来の機能を発揮できていない状態と言えます。

気虚が起こるのは頑張りすぎや冷やしすぎのサインである事が多く、温めて休むことを体が求めているのです。
冷えやすい人は下痢や食欲不振を起こしやすいですし、過労気味の人は風邪を引きやすかったりします。
ですが、気が不足しやすいかどうかは、東洋医学における五臓の強さによって左右されるのです。

脾と肺の気虚との関係
東洋医学で五臓と呼ばれる臓器の中でも、気を作り出す主な臓器は脾と肺になります。
脾は主に膵臓を指し消化吸収を通して食べ物から気を生み出しますが、食べすぎや冷たい物のとりすぎ、不規則な食事で弱ります。
肺は呼吸で気を取り込んで全身に送るとされますが、ストレスが多く呼吸が浅い状態が続くと弱ります。
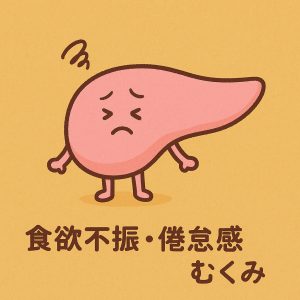
つまり、食生活の乱れで気が作れなくなり、呼吸の浅さで気が巡らなくなるのです。
脾と肺が元気なら体に気が満ちるので、食事と呼吸のバランスが気虚の予防に役立ちます。
残りの五臓である心や腎も脾と肺を助けることで、脾と肺は弱りにくく元気でいられます。
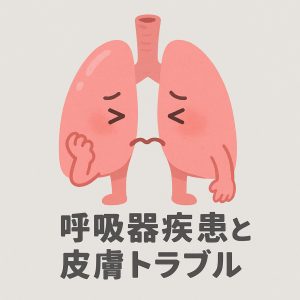
気虚タイプにお勧めのストレッチと薬膳
ストレッチの目的は気の巡りを助け、脾と肺が働きやすい状態を作る事です。
そこでお勧めなのが深呼吸ストレッチで、胸を開いて息を吸い背中を丸めながら吐くのを繰り返すのが効果的です。
両腕を大きく開いて5秒かけて息を吸いながらお腹と胸を伸ばし、体を丸めて背中を伸ばしながら10秒かけて吐きましょう。

次に食事に関しては温めて養うのが基本となるので、冷たいものや生ものは避けて温かい料理を選びましょう。
食材としては米類や芋類、豆類にカボチャや鶏肉、白身魚などがお勧めです。
また、普段から生姜湯などを飲む習慣もお勧めで、ホットの飲み物でこまめに体温を上げて気を満たす生活を始めましょう。

まとめ
気虚とは体のエネルギー不足で機能が低下した状態です。
気虚の原因は主に脾と肺の弱りです。
元気にするには深呼吸して気虚を解消する食材を心がけましょう。