精神の声に耳を傾けていますか?
「イライラする」
「急に落ち込む」
「不安になる」
こんな感情は内臓の弱りかもしれません。
今回のブログを見れば内臓と感情のつながりと、ストレスに強くなる方法が分かります。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。
五臓と感情のつながり
東洋医学では内臓と感情は密接に関係しており、五臓と呼ばれる内臓の状態は特定の感情を引き起こすとしています。
肝が強い人は行動力があり怒りやすいですが、怒りすぎたりイライラし過ぎたりすると肝が弱ります。
心が強い人は普段からテンションが高く喜びやすいですが、楽しい事ばかり追い求めていると心が弱ります。
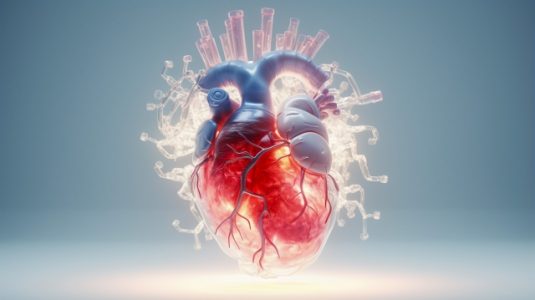
脾が強い人は普段からよく考えるのが癖になっていますが、クヨクヨと悩み過ぎると脾が弱ります。
肺が強い人は普段から感受性が高く内省的ですが、悲観的になり憂いがすぎると肺が弱ります。
腎が強い人は普段から根気強く慎重ですが、恐れ過ぎると腎が弱るというのが東洋医学の考え方です。

怒りっぽい?落ち込みやすい?感情から自分を知る
東洋医学の理論による内臓と感情のつながりでは、肝が強い人ほど怒りやすく落ち込みやすいのが特徴です。
肝が元気な時はエネルギーが余ってストレスに強く怒りやすくなりますが、肝がエネルギー不足になるとストレスに弱くなり落ち込みやすくなります。
つまり、同じ臓器から起こる感情であっても、元気な時とそうでない時では違う感情が湧いてきます。

大切なのは感情を安定させる事であり、感情を安定させるために必要なのは臓器を健康にする事です。
身体が弱るほどに精神的に不安定となり、そうすると普段なら平気な事でも傷ついたり落ち込みやすくなったりします。
そんな時はストレスを発散させる事も大切ですが、まずは身体を休めて内臓を元気にする事が大切なのです。

忙しい時ほど「ゆるむ」時間を
東洋医学では忙しい時ほど負担がかかっているのは肝と心で、ストレスに強い人ほど肝と心が強いと言えます。
ただし内臓が強いという東洋医学の表現は、特別に機能が高いという訳ではなく正常に機能しているという意味です。
東洋医学において身体というのは強くある必要はなく、本来の機能を発揮できていれば十分だと考えます。

現代医学のように鍛える事は必要とせず、本来の機能を発揮して出来る事をきちんとこなす事が大切なのです。
そのため、ストレスに強くなるには負担がかかっても平気な内臓を作るのではなく、休むときは休んで身体の本来の機能を取り戻す事なのです。
そのために必要なのが副交感神経が優位になるリラックス出来る時間で、身体を温めてボーっと出来る時間を作るのは極めて効果的なのです。

まとめ
感情は内臓の機能に左右されています。
イライラする時も落ち込むときも肝臓の影響ですが、肝臓の状態は違います。
大切なのは感情を安定させることで、そのためにボーっとする時間を作る事が必要になります。