身体が痛みやすくなっていませんか?
「頭痛が増えた」
「指が痛む」
「ずっと痛んでいる」
こんな症状は身体で血滞が起こっているかもしれません。
今回のブログを見れば血滞が起こる原因と、解消のためのやっておきたい習慣が分かります。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。
長時間の同じ姿勢は血滞を生む
指に限らずですが、身体が痛む最も大きな原因は運動不足による血行不良です。
東洋医学では血行不良の状態を血滞と呼び、血行不良による痛みが最も強く指先などの末梢で起こりやすいと考えます。
加えて加齢に伴い血行不良は起こりやすくなり、長時間の同じ姿勢は血滞の原因となります。

筋肉に刺激を入れるだけで血滞は起こりにくくなるので、長時間の同じ姿勢を避けるために1時間に1度は立ち上がるのが大切になります。
また、普段から運動をして筋肉を刺激している人は血滞が起こりにくいので、日ごろの運動もポイントになります。
もう一つのポイントは水分補給で、身体が脱水状態の時ほど血滞は起こりやすくなるので水分補給は大切になります。
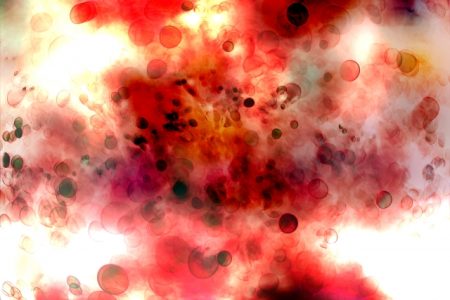
こまめに動く経絡ウォーキング
東洋医学では血滞の原因の一つとして、肝経(かんけい)と呼ばれる足の内側からお腹の外側を通る経絡の流れが悪いと考えます。
肝経は肝臓の経絡なので、運動不足だけでなくお酒の飲み過ぎやストレス、睡眠不足も悪影響します。
長時間の同じ姿勢をするデスクワークは肉体的なストレスとなり、肝経の流れを滞らせて血滞が起こりやすい身体になります。

そこでお勧めなのが経絡ウォーキングで、肝経が通るラインを刺激するために可能なら砂浜などを裸足で歩きます。
足にある経絡は指から始まるので、可能なら裸足か足袋やサンダルなど肝経が通る親指が動きやすい状態で歩きます。
出来る限り歩幅を大きくする事でより経絡を刺激できるので、普段から10~30分くらいのウォーキングを目指しましょう。

昼寝と東洋医学の子午流注(しごるちゅう)
東洋医学では、時刻ごとに臓腑の気血の巡りが変化する子午流注という考え方があります。
この考え方に基づけば、11~13時の間に10~30分くらいの昼寝をする事は心(しん)の働きを助けます。
心は自律神経を整えるのに役立つので、精神と肉体のストレスを和らげるのに役立ちます。

普段から疲労が溜まり睡眠不足な人でも、この時間に軽くでも昼寝をする事で肝の負担を減らし血滞の予防に役立ちます。
ただし、30分以上の睡眠は余計にだるくなるので、昼寝は長くても30分以内に収めるようにしましょう。
大切なのは身体の疲労とストレスを和らげ、筋肉を刺激する事で血滞を予防する事になります。

まとめ
身体が痛むのは主に血滞が原因となります。
血滞は同じ姿勢が長く続くと起こるのでこまめに動くことが大切です。
また、昼寝を取り入れる事は血滞の予防につながります。