秋に調子を崩したことはありますか?
「咳が出やすい」
「便秘をする」
「憂鬱になる」
こんな症状は秋の気候で体調を崩しているかもしれません。
今回のブログを見れば秋に起こりやすい不調の原因と、体調を整える薬膳が分かります。
今回も東洋医学が大好きな鍼灸あん摩マッサージ指圧師の福原がお送りします。
秋に応じた整え方
秋は徐々に乾燥が始まり肺が弱る季節なので、過度に汗をかくのは避けて身体を潤す事を意識しましょう。
加えて秋は日中は暑さが残りますが、朝晩はどんどんと涼しくなるので寒暖差により自律神経が乱れやすくなります。
そのため、秋は適度に身体を動かしながらも激しい運動は避け、体温調節しやすい服装をする事が大切です。

秋の寒暖差と乾燥で肺が弱ると喉や肌の乾燥に喘息などアレルギーの悪化が起こりやすくなります。
東洋医学では肺は大腸と互いに影響し合うので、肺の弱りは大腸も弱らせて便秘の原因にもなります。
さらに肺の弱りは気分の落ち込みなどを引き起こすことがあり、普段よりも悲観的になっていると感じたら水分をとって肺を潤しましょう。

五臓と感情のつながり方
東洋医学では内臓と感情は密接に関係しており、五臓と呼ばれる内臓の状態は特定の感情を引き起こすとしています。
肝が強い人は怒りやすいですが、怒りすぎたりイライラし過ぎたりすると肝が弱ります。
心が強い人は普段からテンションが高く喜びやすいですが、楽しい事ばかり追い求めていると心が弱ります。
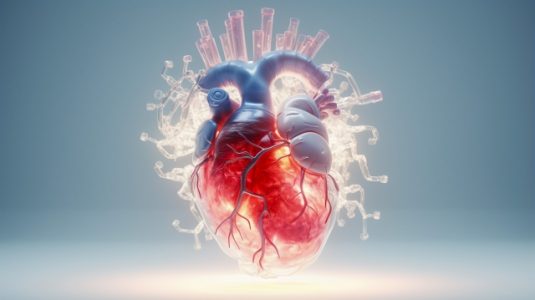
脾が強い人は普段からよく考えるのが癖になっていますが、クヨクヨと悩み過ぎると脾が弱ります。
肺が強い人は普段から反省する事が多いですが、悲観的になり憂いが増えすぎると肺が弱ります。
腎が強い人は普段から慎重になりやすいですが、恐れ過ぎると腎が弱るなどが東洋医学の考え方です。

水を巡らせる食材
梅雨や残暑の時期は水分の巡りが悪くなる水滞が起こりやすくなり、脾が弱る事でさらに症状は悪化します。
また、秋になって肺が弱る事も水滞を起こす原因となり、肺の弱りから水滞が起こるとアレルギーの原因ともなります。
水滞を解消するのに大切なのは、脾と肺の機能を高める食材や利水作用や発汗作用のある食材になります。

脾と肺を助ける食材には身体を潤す山芋やトウモロコシがあり、梨や柿などの秋の果物は身体を潤してくれます。
ハトムギやキュウリなどは利水作用で水滞の解消を助け、トウモロコシは身体を潤して不要な老廃物の排泄を助けます。
水を巡らせ排尿を促すものにはワカメや昆布などの海藻類があり、水分代謝を高める事は残暑から秋を元気に乗り切る秘訣にもなります。

まとめ
秋は乾燥と寒暖差で肺が弱りやすい季節です。
肺の弱りなど内臓の状態は感情に影響します。
肺を元気にして水を巡らす食材で残暑から秋を元気に乗り切れます。